 |
| サイトマップ | |
|
 |
| サイトマップ | |
|
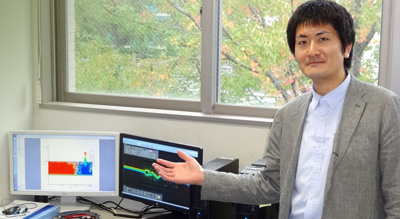 |
東海大学工学部 動力機械工学科 高橋俊 講師 (所属は取材当時のものです) |
 |
今後の様々なものづくりにおける CAE 技術の一環として、高速かつ高精度な流体解析ソルバや、またそれに関連するアルゴリズムの開発を行っています。近年のものづくりの現場で CAE 技術は欠かせないもので、多くの汎用ソフトが使われています。これら汎用ソフトの性能も日々向上して目覚ましい進歩をしていますが、その解析内のアルゴリズムも日々変化・進歩しています。当研究室では、直交格子を活用してこれまで解析フローのボトルネックであった計算格子生成を半自動化し、解析の生産効率を向上させることや、アーキテクチャに応じた大規模解析のアルゴリズム開発などに取り組んでいます。
流体解析と定量的な評価は研究室で開発したプログラムで行い、Tecplot では流体場の可視化による把握を行います。当研究室では複雑な形状もレベルセット関数によって表現するので、使用するデータフォーマットは全て最も単純な PLOT3D フォーマットです。三次元の複雑形状を表現する時のみ Stereolithography (STL) ファイルを用いますが、それも解析内部ではレベルセット関数によって表現されています。主に非定常流体を扱っていますので、Solution 形式によって流れの保存量 (密度、運動量、エネルギ) と、Function 形式によってレベルセット関数を読みこみ、渦度や圧力等の分布を定量的な値と比較しながら調査します。
小規模な解析は研究室のパソコンやワークステーションで行い、中規模から大規模な解析は学内のサーバや外部の大型計算機によって行います。それらの解析結果をネットワークを通じてダウンロードし、研究室内のマシンで可視化を行います。ただあまりに大規模な解析結果の場合にはネットワークを通じたやりとりでは時間がかかり過ぎるため、大型計算機上で直接可視化することを現在検討しています。
以前は様々な可視化ソフトを使っていて、現在は Tecplot をメインに使用しています。その一番の理由は以前マルチブロック型計算格子の流体解析プログラムを開発した際に、ブロックの数が増えると可視化の自由度が制限されるソフトが多かったのですが、Tecplot ではそういった制約が少なかったことです。また、毎年使用している学生たちの様子を見ていても使いやすい印象を持っているようで、可視化ソフトを初めて使う人が多い大学という環境ではこういった第一印象が特に重要なようにも思います。
良い点は、上で述べたように使いやすい印象を与えるユーザインタフェース、軽快な動作と自由度、様々なソフトから得られた結果を読める汎用性、その他にもたくさんあります。特に悪いという点はほとんど感じませんが、アニメーションを作った際に使用したメモリ領域が解放されずに残ってしまい、他のアプリケーションの動作を圧迫する場合があることくらいでしょうか。かなり細かい点ですみません。
当研究室では汎用ソフトがあまり得意でない領域の解析にも取り組んでいます。図1と図2は、多数の粒子を含む流体場において圧力波やその他の流体力学的特性の変化を調査している研究の可視化図です。粒子の周囲には衝撃波と渦度が生じ、それらが周囲の粒子と相互に影響しあいます。またこれらの粒子の解析では粒子間の衝突も考慮することが可能で (図3) 、これらが実際に流れ場や周囲に対してどのように影響するのかを調査しています。この粒子は非常に微細なマイクロメートルオーダの微粒子で、高エネルギの流れ場中を超音速近傍の高速で飛行しています。Tecplot を用いることで、図4のようにより直感的にわかりやすい表現に変更することが容易にできます。
|
|
||
|
|
自作のプログラムを開発する研究者以外にも、汎用ソフトの結果も多数読むことが可能なので広い範囲のエンジニアが使うことができます。2 次元空間の結果を、軸を追加・変更することで容易に3次元化することができ、それによってこれまでに見えなかった現象を見出すことなどもできます。可視化によって情報を抽出することを考えるのであれば、Tecplot は非常に効果を発揮するソフトであると言えます。
本事例作成に関し、高橋 講師のご協力に感謝いたします。
(インタビュー:2014 年10 月)
※所属・役職はインタビュー時のものです。